台風のシーズンが近づくと、気になるのが台風の名前ですよね。特に日本が提案する台風名には「ウサギ」や「ヤギ」といった可愛らしい名前が多く、「なんだかダサい…」と感じる方も多いのではないでしょうか?
実は、この台風の名前には深い意味が隠されているんです。今回は、なぜ台風に名前をつけるのか、どのように決められているのか、そして日本の台風名が「ダサい」と言われる理由について詳しく解説していきます!
台風の名前はなぜ必要?命名の意外な理由とは

台風に名前をつける理由、気になりませんか?実は、これには3つの重要な目的があるんです。
まず、台風の識別を簡単にするためです。同じ時期に複数の台風が発生することもあるため、それぞれを区別しやすい名前をつけることで、気象情報の伝達がスムーズになります。
次に、名前をつけることで、人々の記憶に残りやすくなるという利点があります。特に大きな被害をもたらした台風は、その名前と共に教訓として語り継がれることになります。
そして3つ目は、国際的な情報共有を円滑にするためです。各国の気象機関やメディアが同じ名前を使うことで、混乱なく情報を共有できるんです。
例えば、2019年の台風19号「ハギビス」は、日本各地に甚大な被害をもたらしました。この「ハギビス」という名前は、多くの人々の記憶に強く残り、防災意識を高める役割を果たしています。
また、2018年の台風21号「ジェビ」は、関西国際空港の浸水被害で知られていますが、この名前は韓国が提案したもので「ツバメ」を意味します。国際的にも同じ名前で共有されることで、各国のメディアが正確に報道できました。
日本の台風名が「ダサい」と言われる3つの理由と具体例
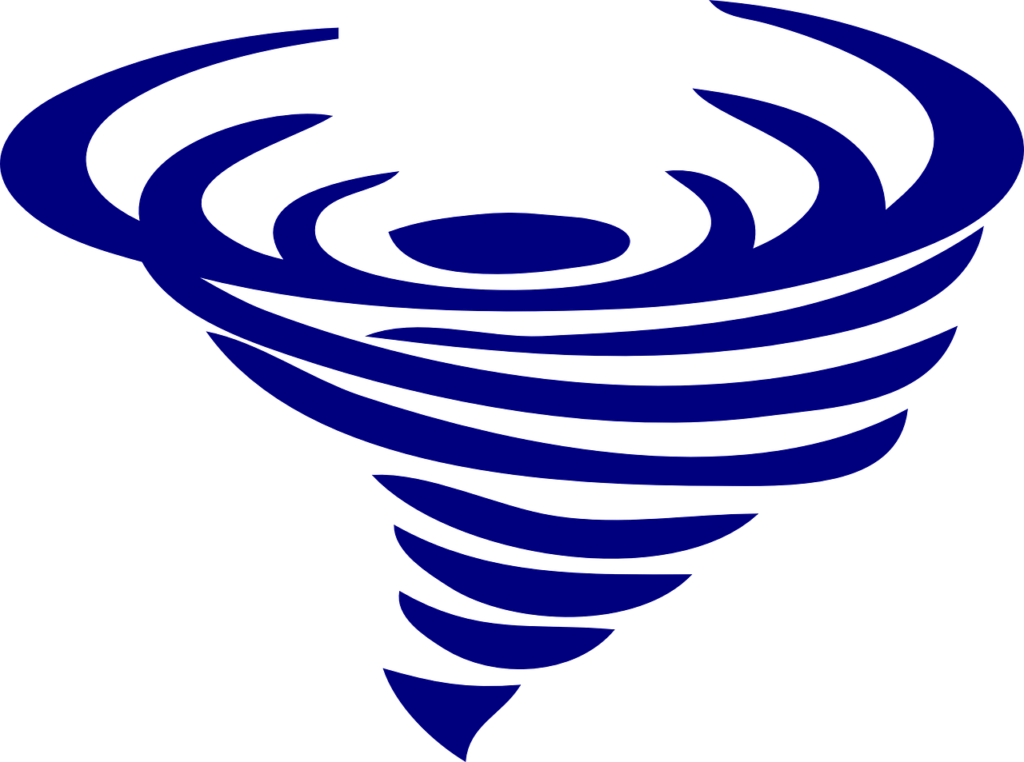
では、なぜ日本の提案する台風名は「ダサい」と言われてしまうのでしょうか?具体例と共に3つの理由を詳しく見ていきましょう。
1つ目は、星座や動物の名前が多いことです。例えば、過去の台風名を見てみると:
- 「コグマ」(小熊座より)
- 「ウサギ」(うさぎ座より)
- 「ヤギ」(やぎ座より)
といった可愛らしい印象の名前が並びます。これらは台風の危険性や威力を十分に伝えきれていないと指摘されています。
2つ目は、他国との比較です。他のアジア諸国の提案する名前を見てみましょう:
- フィリピン:「マリクシ」(速い)、「ヨランダ」(鷹のような)
- タイ:「プラピルーン」(雨の神)、「ノックテン」(鳥の宝石)
- 中国:「ウーコン」(悟空)、「フンシェン」(鳳凰)
これらの名前は、台風の性質や力強さを表現していたり、その国の文化や伝統を反映していたりと、印象的な名前が多いことがわかります。
3つ目は、防災意識との関連です。気象庁が2023年に実施した調査によると、10代~20代の若者の45%が「台風の名前が可愛らしすぎて、危機感を感じにくい」と回答したそうです。
知っておきたい!台風の名前の決め方と国際ルール

台風の名前は、アジア太平洋地域の14の国と地域が協力して決めています。各国が順番に名前を提案し、台風委員会で採用される仕組みになっているんです。
具体的な選定プロセスを見てみましょう:
1. 各国が28個の名前を提案
2. 台風委員会での審査(不適切な意味を持たないかなどをチェック)
3. 140個の名前リストの作成
4. 台風発生時に順番に使用
日本が星座や動物の名前を選ぶ理由には、実は深い配慮が隠されています。他国の言語や文化で不適切な意味を持たないよう、できるだけ中立的な名前を選んでいるのです。
例えば、ある国では縁起が悪いとされる動物や、特定の宗教で神聖視される言葉は避ける必要があります。そのため、日本は比較的無難な星座名や動物名を選択しているわけです。
【新しい視点:防災AI時代における台風名の役割】
最近では、AIを活用した防災システムの発展により、台風名の新しい活用方法が生まれています。例えば:
- AIによる過去の台風データ分析と名前の関連付け
- SNSでの台風関連投稿の自動モニタリング
- 台風名を活用した防災チャットボットの開発
特に注目すべきは、台風名をキーワードとしたSNSの投稿分析です。例えば、「台風○○接近中」というツイートの増加パターンを分析することで、地域ごとの防災意識の高まりを測定できるようになっています。
また、LINEやメッセンジャーで活用される防災チャットボットは、台風名を入力するだけで、その台風の最新情報や避難に関する質問に答えてくれる機能を備えています。
これからの台風名はどうあるべき?専門家の意見と今後の展望
では、今後の台風名はどうあるべきなのでしょうか?気象予報士や防災専門家からは、以下のような具体的な提案が出ています。
1. 防災意識を高める効果的な名前の採用
- 「サンダー」(雷)
- 「ストーム」(暴風)
- 「タイダル」(潮流)
など、自然の力強さを表現する名前の採用が提案されています。
2. 日本の伝統文化を活かした名前の検討
- 「カグツチ」(火の神)
- 「スサノオ」(暴風の神)
- 「ライジン」(雷神)
など、日本神話の神々の名前を使用する案も出ています。
3. 地域特性を反映した名前の提案
- 「アラシヤマ」(嵐山)
- 「ウミカゼ」(海風)
- 「ヤマカゼ」(山風)
といった、日本の地理や気象を表現する名前も候補として挙がっています。
また、防災教育の専門家からは、台風名を活用した新しい防災教育プログラムの提案も出ています。例えば:
- 小学校での「台風名づけワークショップ」の実施
- 中学校での「台風と防災」をテーマにした総合学習
- 高校での「気象と命名の文化」についての探究学習
これらの活動を通じて、若い世代に台風への関心と防災意識を高めてもらうことが期待されています。
【まとめ】
台風の名前は、単なる識別子以上の重要な役割を持っています。防災意識を高め、適切な避難行動を促すためのツールとしても機能しているのです。
確かに日本の台風名は「ダサい」と感じられることもありますが、その背景には深い配慮と意図があることがわかりました。
今後は、文化的配慮を保ちながら、より効果的な防災コミュニケーションを実現する台風名の在り方が求められています。特に、AIやSNSの活用と組み合わせることで、新しい防災・減災の可能性が広がっていくでしょう。
私たちも、台風の名前を通じて、防災意識を高めていく必要がありますね。次に台風のニュースを見たとき、その名前の持つ意味について、ちょっと考えてみてはいかがでしょうか?